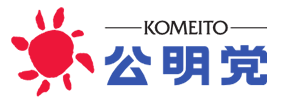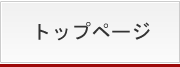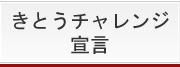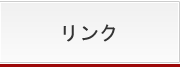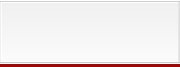大村愛知県知事と国に要望いたしました
7月18日、アジア・アジアパラ競技大会推進愛知県議会議員連盟は、組織委員会会長の大村秀章知事と、文部科学省で安江伸夫政務官(公明党)と面会し、大会を国の主要施策に位置付けることなどを要望しました。私は同議連副会長として参加させていただきました。
国への要望は4回目。6月に閣議決定された政府の「骨太の方針」に、愛知・名古屋大会は「注釈部分」に記載されました。今回はこれより明確に「本文」に位置付け、積極的に推進するように求めました。
安江伸夫政務官からは「経費についてtoto(スポーツ振興くじ)助成金などで支援していきたい」との話がありました。国の積極的な支援に期待が高まる要望会となりました。

地域の声をお聞きして市議県議の連携で実りました
この度、県道14号線(西尾張中央道)一宮市奥町に横断歩道を設置することが出来ました。写真のこの日は、ご要望を頂いた石井さん(写真左)、一宮市議の水谷千恵子さん(写真中央)と設置された横断歩道で喜びを分かち合いました。
昨年の4月、県議会議員選挙の際に、一宮市奥町での集会の終了後に、住民の皆様から「県道を渡る横断歩道を設置してほしい」とのご要望がありました。一宮市の水谷千恵子市議と石井さんがその場にいて、早速現地調査をして私に要望を伝えてくれました。
愛知県警察に要望を伝え、詳しい調査の結果、横断歩道の設置が実現しました。

能登半島地震を訪問してトレーラーハウスの導入を要望
7月1日、公明党の「東海防災・減災力UPプロジェクトの犬飼明佳事務局長と愛知県議団で大村秀章愛知県知事に会い、能登半島地震の課題を踏まえた災害対応能力強化を要望しました。
要望の内容は、家具固定と感震ブレーカー設置の促進、防災士取得費用とボランティアへの補助の創設・拡充、障がい者や女性に配慮した避難所の運営などです。
犬飼事務局長は、被災地を訪れた際に見聞きした避難所トイレの劣悪な状況を強調し「市町村によるトイレトレーラー導入をすすめてほしい」と述べました。大村知事は「要望内容をできる限り取り入れたい」と述べました。

私は、本年2月1日、犬飼さんと能登半島地震の被災地の穴水町の避難所でのボランティア活動を通じて、避難所での被災者の声を教訓として今後の愛知県の防災・減災対策に役立てていきます。特に、室内の家具の固定、避難所での快適なトイレの設置、ボランティアが活動できる体制の早期整備などを今後とも県議会で訴えて実現してまいります。

どなたでも手軽に使える優れた集音器が誕生しました
6月28日、一宮市に本社を置く電子機器開発の株式会社イチワの高木一重社長は、藤田医科大学病院(豊明市)にヘッドフォン型の収音器「エスタス」10台を寄贈しました。
私は長年お付き合いをさせて頂いている高木社長から大学病院へ同機器を寄贈したい旨の要請を受けて、かねてから交流のある藤田医科大学病院を紹介させて頂き、この日の贈呈式が実現しました。

Amazonで購入することが出来ます
収音器は耳の聞こえをサポートする機器で、同社が昨年販売した製品は、太陽光や蛍光灯の明かりで充電ができ、耳に装着するだけで電源が入る特徴があります。
寄贈を受けた同病院の白木良一病院長は、「耳鼻科の診療や高齢者の聞こえにくい人に入院の説明をする際などに活用したい。ニーズが高い製品を頂き、大変ありがたい」と語っていました。
収音器「エスタス」詳しくはココカラ

愛知県のブランド地鶏名古屋コーチンのひなを供給しています
6月4日、愛知県議団で養鶏農家を支える愛知県畜産総合センター種鶏場(小牧市)を訪問し、運営上の課題を聞きました。
種鶏場は、愛知県を代表するブランド地鶏である名古屋コーチンのひなを民間の孵化場に提供する全国唯一の施設です。1938年に安城市に建てられ、老朽化などのため小牧市に移転され、昨年3月に開場しました。鳥インフルエンザ予防、断熱材や衛生面に優れた施設として、ひなの供給能力を強化することができました。
中谷洋種鶏場長からは、年間約100万羽のひなを出荷していると説明があり、「将来的には年200万羽の出荷を目指す上で、人員不足、業務効率化への課題がある」との説明がありました。
畜産総合センター種鶏場ホームページはココカラ

名古屋コーチン
名古屋コーチンは、愛知県を代表するブランド地鶏であるし、県民の食を支える畜産は県政の重要課題です。現場のご意見をもとに後押しをしてまいります。

県営名古屋空港で試験運行の現場を視察しました
5月14日、愛知県議員団で、県営名古屋空港(愛知県豊山町)で実施されているドクタージェットの試験運行を視察しました。これは、医療従事者で作るNPO法人「日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク」(大阪府)が、県営名古屋空港を拠点に本年4月から1年間の予定で実施している試みです。ドクタージェットは、
① 約2000キロの飛行が可能で、全国に出動できる
② 機内が広く、大きな医療機器を載せられる
③ 悪天候時にも飛行でき、揺れが少なく機内で高度な治療が可能
等の利点があります。

運営する中日本航空株式会社の担当者は、高度医療を必要とする金沢市の患者さんへの対応で、ドクターカーとドクタージェットを組み合わせて愛知県へ搬送した事例を紹介されました。その際、「ドクタージェットにより救える命が増える」と強調しました。
一方、運用面で資金に課題があることを述べ、「試験運行の効果を国に示し、国の事業で行われることを目指している」と語っていました。
今後は、医療体制を強化するために重要な取組ですので、公明党としてできることを考えていく必要があると感じました。
ドクタージェット詳しくはココカラ

能登半島地震を教訓に南海トラフ地震に備える質問
3月4日、定例議会の一般質問に立ちました。
愛知県の地震防災対策について
(1)住宅の耐震化に向けた周知・啓発及び支援について
(2)所有者等の事情を考慮した多様な耐震対策について
(3)家具の固定の推進について
(4)中山間地等における孤立対策について
(5)避難所の食事のアレルギー対策について
以上の5つの質問をいたしました。本年元旦に発生した能登半島地震では200名を超える死傷者が出ました。謹んでお悔やみ申し上げます。愛知県でも危惧される南海トラフ大地震に備えて、能登半島で起こった災害を教訓とさせていただき、事前の備えをすべきであると訴えました。

大村知事からは、「現行の耐震改修促進計画では、住宅の耐震化の目標として、二〇二五年度までに耐震化率九五%、二〇三〇年度にまでに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消を掲げておりますので、引き続き、市町村や大学、建築関係団体と連携をいたしまして、住宅の耐震化、減災化により地震から県民の皆様の命を守るよう、そうした取組を全力で進めてまいります。」との答弁がありました。

被災住宅の現場で見たものを今後の防災減災活動に生かします
2月2日、元旦に発生した能登半島地震の被災地、穴水町にて、元県議の犬飼明佳さんと二人でボランティア活動に参加させて頂きました。穴水町では春夏秋冬四季折々の旬の能登の味覚(=まいもん)を楽しめる「穴水まいもんまつり」が行われる予定でした。今年度は1月6日から「かきまつり」が行われる予定でした。しかしかないませんでした。
避難所を拠点に被災者の住宅内の壊れた家具等の運び出しや、落ちた瓦の清掃をいたしました。

2月3日には、危険度判定で住めない自宅に泥棒や不審者が入らないように、ブルーシートで出入り口をふさぎました。震災の混乱に乗じて犯罪を犯す輩は許せないと思います。
避難所では、ご高齢の避難者からのご要望を聞くことが出来ました。
また、とても気になったのがトイレの問題です。水洗トイレが1か月間使えなくて、冬の時期の外の仮設トイレはとても辛い思いをされていることを目の当たりにしました。行政の方も、自分も被災者でありながら、被災住民の為に精いっぱいの仕事をされていました。今後は愛知県の防災減災対策にこの体験を生かしてまいります。

4分野122項目はいづれも県民生活に密着した課題を取り上げました
1月23日、愛知県議団は県公館で大村秀章愛知県知事に対し、2024年度予算編成に関する要望書を提出いたしました。
要望の内容は、
① 妊娠・出産期から切れ目ない支援を実施するための産前産後ケアの充実
② 民間木造住宅の耐震化と家具などの転倒防止策の促進
③ 教員の質向上と働き方改革の推進
など、4分野122項目を求めました。大村知事からは前向きに取り組み考えが示されました。

大村愛知県知事に要望書を提出
6月8日午後、命にかかわる病気や障害のある子どもが、家族とともに過ごせる施設「こどもホスピス」を県内につくりたいと、NPO法人「愛知こどもホスピスプロジェクト」の皆様と公明党愛知県議員団とで大村愛知県知事にこどもホスピスを愛知県内に開設することへの支援を要望いたしました。

関東と関西には、医療機関や民間団体が運営するこどもホスピスがあるが、東海3県にはありません。大学病院の医師や患者の家族の方により4月にNPOを設立しホスピス開設を進めています。要望では、県有地の貸与や運営費の補助を検討するよう求めています。また、命にかかわる病気や障害のある子どもと家族に関する実態調査や、子どもに関する県の総合計画にこどもホスピスヘの支援を盛り込むことも求めています。
大村知事は「いただいた要望はしっかり受け止め、皆さんと意見交換しながら検討したい」と話しました。
NPO法人愛知こどもホスピスプロジェクトはココカラ